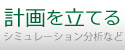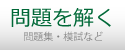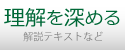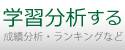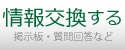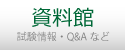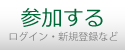社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1380. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
[自説の根拠]則18条
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
830
[問題文]
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長を経由するものとされている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1379. ymamn6314 さん
[コメント]
社会復帰促進等事業に要する費用及び労災保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、労働保険料の額その他の収入額の合計額に118分の18を乗じた額に、雑収入の額等を加えた額を超えないものとする
[自説の根拠]施行規則43条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3225
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。
労働福祉事業に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額については、現行法令上制限されている。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1378. papatarou さん
[コメント]
船舶所有者はなぜ除かれるのでしょうか?どなたか教えてください。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
969
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を社会保険事務所長等に届け出なければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1377. mayunavi さん
[コメント]
被保険者または被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認日の属する月前10年以内の期間に限り、法定免除、申請免除、または学生納付特例の規定により納付することを要しないとされた保険料の全部または一部につき追納することができる。
[自説の根拠]国民年金法第94条
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2375
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1376. ninyan さん
[コメント]
老齢基礎年金の受給権者は受給内容が確定しているので追納することはできない。なお、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給権者は追納することができる。
[自説の根拠]法第94条第1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2375
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1375. seiseki2743 さん
[コメント]
当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1819
[問題文]
次の説明は、平成16年改正に関する記述である。
平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に参入されない期間がある場合には、社会保険庁長官に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に参入することとした。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1374. seisin0926 さん
[コメント]
時限措置ではありません。
混乱しやすいのは同時期の法改正による時限措置。
30歳未満の第1号被保険者に対する納付猶予措置(平成27年6月まで)があります。
[自説の根拠]法附則19条 1項2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1819
[問題文]
次の説明は、平成16年改正に関する記述である。
平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に参入されない期間がある場合には、社会保険庁長官に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に参入することとした。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1373. naito0101 さん
[コメント]
「任意適用事業所取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、厚生労働大臣に申請しなければならない」
なお、厚生労働大臣による取消し認可の権限は、全国健康保険協会管掌健康保険は社会保険事務局長、社会保険事務所長に、また組合管掌健康保険は地方厚生局長、地方厚生支局長に委任されている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1081
[問題文]
次の説明は、健康保険の適用事業所に関する記述である。
任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、社会保険事務所長・社会保険事務局長又は地方厚生局長・地方厚生支局長に提出することによって行う。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1372. ymamn6314 さん
[コメント]
H22法改正により、「任意適用事業所取り消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、厚生労働大臣に申請しなければならない」(33条)
また、厚生労働大臣による任意適用の認可・取り消しは、
・全国健康保険協会管掌健康保険:機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(204条)→日本年金機構
・組合管掌健康保険:地方厚生局長等への権限の委任(205条)→地方厚生局長、地方厚生支局長
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
1081
[問題文]
次の説明は、健康保険の適用事業所に関する記述である。
任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、社会保険事務所長・社会保険事務局長又は地方厚生局長・地方厚生支局長に提出することによって行う。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1371. ymamn6314 さん
[コメント]
法定免除のいずれにも該当しなくなった時は、保険料の免除理由に該当しなくなった理由・その該当しなくなった年月日などを記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、機構に提出しなければならない。ただし、
①以前から、法定免除(全額免除)ではなくて半額免除にしておいたとき、
②法定免除不該当日から14日以内に、何らかの免除申請あるいは納付特例を申請したとき、
③厚生労働大臣が市町村などから法定免除のいずれにも該当しなくなった確認を得たとき、
は届出は不要としている。
[自説の根拠]施行規則76条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3661
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日