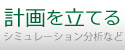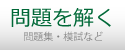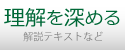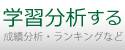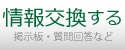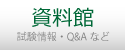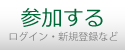社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1400. d931f3ad2628 さん
[コメント]
雇用保険二事業については保険給付ではありませんので、処分に不服があっても雇用保険審査官に対して審査請求をすることができません
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1388
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
行政庁が雇用保険三事業の給付金を支給しないことについて不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をする権利を有する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1399. ninyan さん
[コメント]
雇用保険二事業については法69条の行政処分にあたらないので、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができず、原則に立ち返り、行政不服審査法に基づいて処分庁への異議申立て、上級処分庁への審査請求などの不服の申し立てを行う。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1388
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
行政庁が雇用保険三事業の給付金を支給しないことについて不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をする権利を有する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1398. seiseki2743 さん
[コメント]
・前期高齢者納付金
・後期高齢者支援金
・病床転換支援金
・介護納付金
についての国庫補助割合は、164/1,000
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3139
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
政府管掌健康保険が納付する老人保健法の規定による医療費拠出金に対する国庫補助の割合は現在1000分の130である。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1397. marurumaruru さん
[コメント]
(届出等)
第百五条
4 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
とあるので本問は正解となる。
[自説の根拠]国民年金法 第105条 第4項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2715
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を社会保険庁長官又は市町村長に届け出なければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1396. cock55 さん
[コメント]
設問の者については、老齢・退職を支給事由とする給付の受給権を有しない者は、受給期間を満たすまで任意加入が可能だが、ただし、社会保険庁長官に申し出る必要がある。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
958
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、社会保険庁長官に申し出る必要がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1395. chantoha6161 さん
[コメント]
高齢任意加入被保険者
●適用事業所に使用される70歳以上の者(保険料全額負担)
→ 事業主の同意不要
→ 厚生労働大臣への申し出
●適用事業所に使用される70歳以上の者(保険料半額負担)
→ 事業主の同意が必要
→ 厚生労働大臣への申し出
●適用事業所以外に使用される70歳以上の者
→ 事業主の同意が必要
→ 厚生労働大臣の認可
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
958
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、社会保険庁長官に申し出る必要がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1394. suzukyo さん
[コメント]
高齢任意加入被保険者
●適用事業所に使用される70歳以上の者
→ 事業主の同意は必要なし
→ 社会保険庁長官、申し出る
●適用事業所以外に使用される70歳以上の者
→ 事業主の同意が必要
→ 社会保険長長官、認可を受ける
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
958
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、社会保険庁長官に申し出る必要がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1393. marurumaruru さん
[コメント]
(届出)
第十二条
5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法 若しくは地方公務員等共済組合法 の組合員又は私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
9 第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。
正解
[自説の根拠]国民年金法 第12条 第9項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1670
[問題文]
次の説明は、国民年金の事務に関する記述である。
第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があったものとみなす。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1392. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることをを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六ヶ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
[自説の根拠]第83条 第2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1597
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、社会保険庁長官は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1391. seisin0926 さん
[コメント]
納付した日から起算して6か月以内⇒納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内
[自説の根拠]法83条2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1597
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、社会保険庁長官は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日