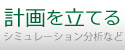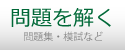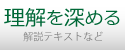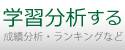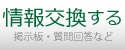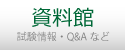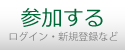社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1520. prinpa さん
[コメント]
この部分の根拠法令みつけました。
[自説の根拠]徴収法施行令第1条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1754
[問題文]
次の説明は、労働保険料に関する記述である。なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1519. prinpa さん
[コメント]
日雇労働被保険者は、高年齢労働者の保険料免除の対象にはなりません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1754
[問題文]
次の説明は、労働保険料に関する記述である。なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1518. seiseki2743 さん
[コメント]
「短時間労働被保険者」ではなく、「短期雇用特例被保険者」である。なお、平成19年10月から短時間労働被保険者の被保険者区分がなくなり、一般被保険者として一本化されている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1754
[問題文]
次の説明は、労働保険料に関する記述である。なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1517. ponchan さん
[コメント]
保険年度の初日(4月1日)に64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)がいる場合には、その者の雇用保険の保険料が免除される。
従って、当時も今も×
[自説の根拠]法11条の2とその関連附則等
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1754
[問題文]
次の説明は、労働保険料に関する記述である。なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1516. hirorin さん
[コメント]
法改正で平成19年10月1日より、短時間労働被保険者、短時間労働被保険者以外の被保険者という被保険者区分の規定が廃止されました。
当時日雇労働被保険者についての問題文の記述は正しかった(現行でも正解)が、「短時間労働被保険者」については保険年度の初日において満64歳以上である場合、保険料免除の対象になっていたため問題文は誤りであった。
なお、保険年度の初日において満64歳以上であって、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象になるのは、一般被保険者及び高年齢継続被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については保険年度の初日において満64歳以上であっても、保険料免除の対象にならない。
[自説の根拠](法11条の2、令1条、則15条の2)
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1754
[問題文]
次の説明は、労働保険料に関する記述である。なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1515. maruta さん
[コメント]
保険年度の初日で64歳以上の一般被保険者及び高年齢継続被保険者は雇用保険を免除される。保険料免除の対象にならないのは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1754
[問題文]
次の説明は、労働保険料に関する記述である。なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1514. zeroclown さん
[コメント]
法律改正により、社会保険庁長官から厚生労働大臣になりました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
3648
[問題文]
次の説明は、国民年金保険料の前納又は追納に関する記述である。
保険料の前納は、社会保険庁長官が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1513. kido1868 さん
[コメント]
社会保険庁長官→厚生労働大臣
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
3648
[問題文]
次の説明は、国民年金保険料の前納又は追納に関する記述である。
保険料の前納は、社会保険庁長官が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1512. suzukyo さん
[コメント]
高齢者の医療の確保に関する法律
費用の負担について
後期高齢者医療制度における療養の給付等に要する費用の額については、一部負担金を除き、その5割を公費により負担し、4割を各医療保険の被保険者(後期高齢者交付金)、1割を後期高齢者医療の被保険者が負担する。
公費5割は 国4:都道府県1:市町村1
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
278
[問題文]
次の説明は、老人保健法に関する記述である。
国は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の1を負担する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1511. tanuki さん
[コメント]
医療等に要する費用(特定費用は除く)についてはその12分の4を負担することになっている
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
278
[問題文]
次の説明は、老人保健法に関する記述である。
国は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の1を負担する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日