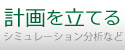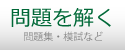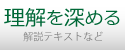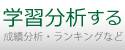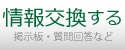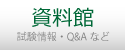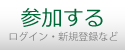社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1350. marurumaruru さん
[コメント]
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三十四条
3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
社会保険庁長官⇒厚生労働大臣
一年を経過した日「後」
[自説の根拠]国民年金法 第34条 第3項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
593
[問題文]
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は社会保険庁長官が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1349. seiseki2743 さん
[コメント]
障害基礎年金額の改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
593
[問題文]
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は社会保険庁長官が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1348. seisin0926 さん
[コメント]
経過した日⇒経過した日の後
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
593
[問題文]
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は社会保険庁長官が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1347. d931f3ad2628 さん
[コメント]
社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2991
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1346. vickyvale さん
[コメント]
「市町村長を経由して」ではなく、「直接」交付する。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2991
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1345. marurumaruru さん
[コメント]
厚生労働大臣(事務は日本年金機構)から直接交付。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2991
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1344. seiseki2743 さん
[コメント]
社会復帰促進等事業は、政府が行う。
社会復帰促進事業のうち一部のもの
① 労災病院等の設置・運営、健康診断センター等の設置及び運営
② 未払賃金の立替払事業等
は、独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせることとしている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1187
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
労働福祉事業は、原則として、機構が統括して行うこととなっている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1343. gokaku100 さん
[コメント]
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出。
厚生年金保険の被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、社会保険事務所長等に提出。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
1699
[問題文]
次の説明は、健康保険と厚生年金保険の届出・手続きに関する記述である。
健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、従業員を採用したときは、被保険者の資格取得の届出を社会保険事務所長等又は健康保険組合に5日以内に行わなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1342. seiseki2743 さん
[コメント]
第3号被保険者に係る被扶養配偶者が、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、社会保険庁長官の定めるところにより、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
625
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、社会保険庁長官の定めるところにより、市町村長が行う。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1341. ymamn6314 さん
[コメント]
H22.1.1の法改正により、「第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の定めるところにより、日本年金機構が行う」となった。
[自説の根拠]施行令4条の2
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
625
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、社会保険庁長官の定めるところにより、市町村長が行う。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日