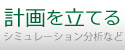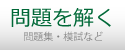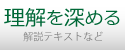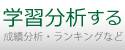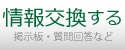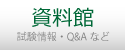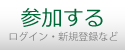社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1360. 563de7334064 さん
[コメント]
日本年金機構が行うとなっていました。
(被扶養配偶者の認定)
法第七条第二項 に規定する主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法 及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
[自説の根拠]令第4条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
625
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、社会保険庁長官の定めるところにより、市町村長が行う。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1359. nnnyyaa さん
[コメント]
<地方社会保険事務局長>→<厚生労働大臣>
※地方社会保険事務局は、平成21年12月31日限りで廃止された社会保険庁が設置していた地方支分部局である。
[自説の根拠]老齢福祉年金支給規則 第5条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1826
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年8月11日から9月10日までの間に地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1358. tatsu1962 さん
[コメント]
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得状況届に、前年の所得額を証明する書類等を添えて、毎年8月11日から9月10日までの間に、地方社会保険事務局長に提出しなければならないことになっている。
なお、老齢福祉年金が全額支給停止されているとき、又は、老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する老齢福祉年金所得状況届が既に提出されているときは提出する必要はない。
この問題って国民年金じゃない。
[自説の根拠]老齢福祉年金支給規則5条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1826
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年8月11日から9月10日までの間に地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1357. ymamn6314 さん
[コメント]
「生存の確認」=「現況届」
平成18年の法改正により、簡素化を図る目的により現況届の提出は不要となりました。社会保険庁長官は、原則として年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定によるその支払期月に支給する年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされています。なお、必要に応じ、年金給付の受給権者に対し、その者の住民票コードの報告を求めることができます。
[自説の根拠]則35条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1260
[問題文]
次の説明は、受給権者の届出に関する記述である。
社会保険庁長官が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1356. satotas さん
[コメント]
×種別変更 → ○種別確認
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
207
[問題文]
次の説明は、届出に関する記述である。
第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を社会保険庁長官に行わなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
○
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1355. ninyan さん
[コメント]
第3号被保険者が披扶養配偶者でなくなったか否かについては触れられていないが、引き続き披扶養配偶者であるときは、「種別の変更の届出」ではなく「種別確認の届出」(配偶者が厚生年金保険被保険者の資格を喪失して共済組合等の組合員又は加入者の資格を取得した等の場合の届出)を行います。
[自説の根拠]国民年金法第12条第5項 国民年金法施行規則第6条の2,第6条の3
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
207
[問題文]
次の説明は、届出に関する記述である。
第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を社会保険庁長官に行わなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1354. ymamn6314 さん
[コメント]
法改正により、種別確認の届出先は、日本年金機構となる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
207
[問題文]
次の説明は、届出に関する記述である。
第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を社会保険庁長官に行わなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1353. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
「法定受託事務」
[自説の根拠]第5条の3
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2993
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金法に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、市町村長に委任することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1352. tokisude さん
[コメント]
市町村長ではなく、地方社会保険事務局長に委任することができます(法5条の2第1項)。
それをさらに社会保険事務所長に委任することもできます(法5条の2第2項)。
市町村長に権限委任できる旨の規定はありません。
なお、法5条の3に一定の事務を市町村が処理するという規定がありますが、これはあくまでも事務処理を行うだけであって、権限の委任ではありません。
[自説の根拠]国民年金法5条の2、5条の3
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2993
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金法に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、市町村長に委任することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1351. uechan さん
[コメント]
前回コメント訂正
改正で大臣の権限の一部は、「地方厚生局長」に委任することができる。またその権限は、「地方厚生支局長」に委任することができる。 日本年金機構は一部の事務をおこなう。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2993
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金法に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、市町村長に委任することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日