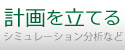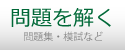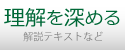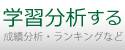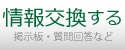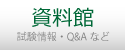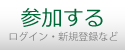社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1600. tokisude さん
[コメント]
国民年金法94条です。
[自説の根拠]http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html#1000000000000000000000000000000000000000000000009400000000001000000000000000000
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1266
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、社会保険庁長官の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1599. seiseki2743 さん
[コメント]
【7月1日】【17日】【その年の9月から翌年の8月】【17日】
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
735
[問題文]
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
社会保険庁長官は、被保険者が毎年【X】現に使用される事業所において、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が【 】未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された標準報酬月額は、【 】までの各月の標準報酬月額とする。
社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、【 】以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
[正解回答]
7月l日
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1598. seiseki2743 さん
[コメント]
資格を喪失した日から起算して、「6月以内」に社会保険庁長官に申し出ることにより、第4種被保険者となることができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1703
[問題文]
次の説明は、健康保険と厚生年金保険の届出・手続きに関する記述である。
第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に年金手帳を添えて退職後3か月以内に社会保険事務所等に提出しなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1597. hakka3 さん
[コメント]
●参考--「2008年労働組合基礎調査」全国調査結果(平成20年6月30日現在、同年12月公表)
<全体>(カッコ内は前年比)
・労働組合数:26,965組合(1.0%減少)
・同組合員数:1,006万5千人(0.1%減少)
・推定組織率: 18.1%(横ばい)※数年来微減の傾向
・傾向の特徴:大規模企業での組合員増加と中小労組での組合員数減少
<パートタイム労働の組合員>(カッコ内は前年比)
・組合員数: 61万6千人(4.7%増加)
・推定組織率:5.0%(0.2%ポイント増加)※数年来増加の傾向にあり
[自説の根拠]『2008年労働組合基礎調査』(厚生労働省)
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1985
[問題文]
次の説明は、賃金等に関する記述である。
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずかに低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パートタイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者にかかる推定組織率は3%を下回る状況である。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1596. ymamn6314 さん
[コメント]
国民年金法に定める厚生労働大臣(法改正により、社会保険庁長官→厚生労働大臣)の権限は、法改正により機構及び財務大臣、地方厚生局長に委任されており、都道府県知事には委任されていないと思う。
なお、市町村長(特別区の区長含む)に対しては、第1号法定受託事務(都道府県知事に対しての場合は第2号法定受託事務)として行う事が出来る。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2992
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金法に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、都道府県知事に委任することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1595. ymamn6314 さん
[コメント]
適用事業所に使用される日雇労働者は日雇特例被保険者となります。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の①~③に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものは、日雇特例労働者とならないことができます。
①適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであること。
②任意継続被保険者であるとき。
③その他特別の理由があるとき。(例えばアルバイトや副業として日雇で働いている場合など)
※法改正により、社会保険庁長官→厚生労働大臣の承認を受けることになりました。
[自説の根拠]3条2項
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
33
[問題文]
次の説明は、日雇特例被保険者に関する記述である。
農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、社会保険庁長官の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1594. running さん
[コメント]
補足:昼間学生が夏季休暇期間中等に日雇労働者として使用される場合もあてはまります
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
33
[問題文]
次の説明は、日雇特例被保険者に関する記述である。
農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、社会保険庁長官の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1593. marurumaruru さん
[コメント]
夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定にあたっては、年間収入の多いほうの被扶養者とするのを原則とするも、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとされる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1106
[問題文]
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。
政府管掌保険における夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、当該家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときは、年間収入の少ない方の被扶養者として認定してよいこととされている。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1592. maruta さん
[コメント]
問題分の「特定受給資格者」を「特定理由離職者」に変更すべきではないでしょうか。
特定受給資格者⇒倒産、解雇等により離職した者。
特定理由離職者⇒有期労働契約が満了し、かつ更新が無くて離職した者。正当な理由により離職した者。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等である場合は、正当な理由より離職した者として特定理由離職者となる場合があります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
1030
[問題文]
次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。
体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定受給資格者に該当することはない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1591. susumu さん
[コメント]
いかなる場合でもが誤り。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
1030
[問題文]
次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。
体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定受給資格者に該当することはない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日