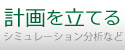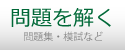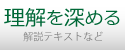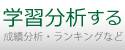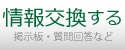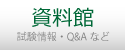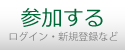社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1630. kaze00 さん
[コメント]
その日から→その日に
「その日から」とは言葉を変えれば「その日以後」となり、本文は×となるのでは。。。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1873
[問題文]
次の説明は、被保険者に関する記述である。
特例退職被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1629. kamegon さん
[コメント]
「その日」が正しい。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1873
[問題文]
次の説明は、被保険者に関する記述である。
特例退職被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1628. kencha さん
[コメント]
特例退職被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となったときは、「その日」に喪失します。
[自説の根拠]自説の根拠は、法附則3条6項プラス「ユーキャン」のテキスト「健康保険法2009年度版」
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1873
[問題文]
次の説明は、被保険者に関する記述である。
特例退職被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1627. seisin0926 さん
[コメント]
法附則3条6項に「特例退職被保険者はこの法律の規定においては任意継続被保険者とみなす。」とあります。
また
法38条は任意継続被保険者の資格喪失についてですが
「第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4.被保険者となったとき。
5.船員保険の被保険者となったとき。
6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき。」
となっていますのでその日に資格喪失となります。
[自説の根拠]法38条 法附則3条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1873
[問題文]
次の説明は、被保険者に関する記述である。
特例退職被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1626. ninyan さん
[コメント]
特例退職被保険者が後期高齢者医療の被保険者等となったときは「その翌日」に資格喪失することになっている。国民健康保険法の規定による退職被保険者資格がなくなったときも同様。
[自説の根拠]法38条1項、法附則3条6項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1873
[問題文]
次の説明は、被保険者に関する記述である。
特例退職被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1625. seiseki2743 さん
[コメント]
後期高齢者医療の被保険者となったときは、「その日」に資格を喪失するのでは?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
1873
[問題文]
次の説明は、被保険者に関する記述である。
特例退職被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1624. onelove さん
[コメント]
保険料半額免除期間は保険料納付済期間の「4分の3」として評価される。
が正解ではないでしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
1636
[問題文]
次の説明は、保険料に関する記述である。
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1623. seisin0926 さん
[コメント]
国庫負担割合が2分の1に引き上げられるまでの期間については国庫負担割合を3分の1として計算する。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1636
[問題文]
次の説明は、保険料に関する記述である。
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1622. okachan さん
[コメント]
本則は4分の3なので、他の問題集の回答は、「×」でした。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1636
[問題文]
次の説明は、保険料に関する記述である。
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1621. seiseki2743 さん
[コメント]
本則上は保険料半額免除期間(480月から保険料納付月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とした月数)は、保険料納付済期間の4分の3として評価されることになっているが、国庫負担割合を2分の1に引き上げるまでの経過措置期間として、平成18年7月から特定月の前月までの月分として支給される老齢基礎年金の額を計算する場合については3分の2として評価されることになっている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1636
[問題文]
次の説明は、保険料に関する記述である。
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日