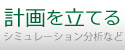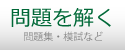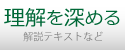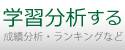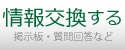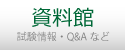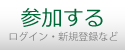社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1650. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
昭和60年改正法の規定による改正前の法による脱退手当金を受ける権利を裁定する権限は、地方社会保険事務局長に、社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。
[自説の根拠]施行令第1条 第1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2361
[問題文]
次の説明は、権限の委任等による地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長の権限に関する記述である。
社会保険事務所長は、昭和16年4月1日前に生まれた者について、その者の昭和60年改正前の厚生年金保険法による脱退手当金を受ける権利を裁定する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1649. ymamn6314 さん
[コメント]
保険料の掛捨て防止を目的とするため脱退手当金が設けられていた。
脱退手当金は次の要件全てを満たした場合支給
①S16.4.1以前に生まれた者であること
②厚生年金保険の被保険者期間が5年以上あること
③老齢年金(老齢厚生年金を含む)を受けるのに必要な期間を満たしていないこと
④60歳に達していること
⑤被保険者資格を喪失していること
⑥通算老齢年金又は障害年金(障害厚生年金を含む)の受給権がないこと(遺族厚生年金や旧法の遺族年金の受給権者であることを理由として、脱退手当金が不支給とされることはない)
⑦過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の支給を受けていないこと(過去に障害年金又は障害手当金の支給を受けた事があっても、その額が脱退手当金の額未満である場合は、その差額が脱退手当金の額とされる)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2361
[問題文]
次の説明は、権限の委任等による地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長の権限に関する記述である。
社会保険事務所長は、昭和16年4月1日前に生まれた者について、その者の昭和60年改正前の厚生年金保険法による脱退手当金を受ける権利を裁定する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1648. kazuaki さん
[コメント]
厚生労働大臣が定める。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3598
[問題文]
次の説明は、被保険者等に関する記述である。
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額はその地方の時価によって、社会保険庁長官が定める。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1647. kuruza77 さん
[コメント]
基金が裁定します 法134条
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3714
[問題文]
次の説明は、社会保険に関する一般常識に関する記述である。
厚生年金保険法によると、厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、社会保険庁長官が裁定する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1646. kyouko さん
[コメント]
【×60歳以上65歳未満】【任意加入被保険者】【65歳】
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
3799
[問題文]
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「若年者納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって【X】であるもの(【 】でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、【 】に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
[正解回答]
60歳以上65歳未満
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1645. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
「あらかじめ」→「速やかに」
[自説の根拠]則第25条 第3項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
968
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは、あらかじめ、これを社会保険事務所長等に届け出なければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1644. seisin0926 さん
[コメント]
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から年金額が改定されることになっており、改定請求をする必要はない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2007
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
遺族厚生年金の受給権者で配偶者以外の者が2人いる場合に、そのどちらかが死亡した場合には、残りの受給権者は社会保険庁長官に対して年金額の改定請求を行わなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1643. seiseki2743 さん
[コメント]
1級又は2級の障害状態にある子又は孫が20歳に達したときは、遺族厚生年金の受給権は消滅するが、受給権の失権の届出を社会保険庁長官に行う必要はない。(18歳到達により失権した場合も同様)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2344
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
1級又は2級の障害の状態になる子が20歳に達して遺族厚生年金の受給権が消滅した場合には、10日以内に当該受給権の失権の届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1642. hirorin さん
[コメント]
H22.1/1~社会保険庁廃止により、「地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に」提出が「日本年金機構又は健康保険組合」となります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3448
[問題文]
次の説明は、報酬及び標準報酬に関する記述である。
事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1641. okachan さん
[コメント]
現在、権限は、地方厚生局長に委任されており、委任された権限のうち、地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
[自説の根拠]法205条、 則 159条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
37
[問題文]
次の説明は、届出等に関する記述である。
指定訪問看護事業者の指定・指定取消、変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限は、地方社会保険事務局長への委任を経て、社会保険事務所長に委任されている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日