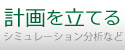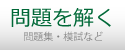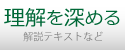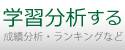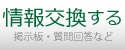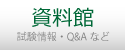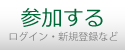社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1670. maruta さん
[コメント]
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。 この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
[自説の根拠]法10条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
573
[問題文]
次の説明は、任意単独被保険者に関する記述である。
任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1669. hirorin さん
[コメント]
H22年1月以降、「社会保険庁長官」→「厚生労働大臣」です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
573
[問題文]
次の説明は、任意単独被保険者に関する記述である。
任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1668. hirorin さん
[コメント]
行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
よって、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときであれば、雇用保険二事業に関することであっても立入検査の権限が認められることになる。
[自説の根拠]法79条1項
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1389
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険三事業に関しても、行政庁の職員が適用事業所に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査を行う権限が認められている。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1667. kaze00 さん
[コメント]
平成22年1月1日に日本年金機構が設立され国民年金法の本則および附則中の社会保険庁長官は厚生労働大臣に改められた。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1671
[問題文]
次の説明は、国民年金の事務に関する記述である。
保険料の申請免除の処分に係る社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任されている。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1666. kaykoma さん
[コメント]
社会保険事務所は年金事務所になったと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1671
[問題文]
次の説明は、国民年金の事務に関する記述である。
保険料の申請免除の処分に係る社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任されている。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1665. jeboys さん
[コメント]
ご存知の通り92条1項は、今年度改正になり、社会保険庁長官から厚生労働大臣になりました。したがって現在はこの文章であると×となります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2048
[問題文]
次の説明は、国民年金の被保険者に関する記述である。
第1号被保険者に対しては、社会保険庁長官から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1664. marurumaruru さん
[コメント]
第九十二条 社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
[自説の根拠]国民年金法 第92条1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2048
[問題文]
次の説明は、国民年金の被保険者に関する記述である。
第1号被保険者に対しては、社会保険庁長官から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1663. ukaruzo さん
[コメント]
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者=当然に65歳以上
20歳前障害は勿論、通常の事後重症も請求できない。
というか問題文の誤りでしょう。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1835
[問題文]
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1662. ymamn6314 さん
[コメント]
繰上支給による影響
①減額された年金が、生涯支給される
②付加年金も同率で減額される
③寡婦年金は65歳到達とみなされ支給されない
④60歳以上65歳未満の者の障害基礎年金、事後重症による障害基礎年金、20歳前の傷病に基づく事後重症による障害基礎年金、その他障害による額の改定、支給停止後のその他障害との併合認定は、65歳到達とみなされるため発生しない。
⑤任意加入はできない
⑥振替加算は影響を受けない(65歳からの減額はされず支給される)
[自説の根拠]附則9条の2の3
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1835
[問題文]
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1661. susumu さん
[コメント]
老年基礎年金の繰上げ受給者には、20歳前傷病による障害基礎年金は支給されない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
1835
[問題文]
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日