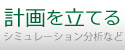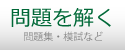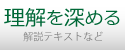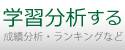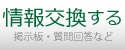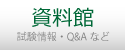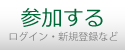社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1730. kazusapapa さん
[コメント]
初受験の人は絶対間違ってしまいます。
その事業、聞いたことなかった。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
3226
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。
労働福祉事業の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1729. ponchan さん
[コメント]
「労働福祉事業」そろそろ修正しないと。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3226
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。
労働福祉事業の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1728. seiseki2743 さん
[コメント]
問題文の訂正
「労働福祉事業」ではなく、「社会復帰促進等事業」であある。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
3226
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。
労働福祉事業の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1727. 1823ur さん
[コメント]
労働福祉事業→社会復帰促進等事業
厚生労働大臣→都道府県労働局長
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1191
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1726. okachan さん
[コメント]
上記プラス「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」については、特別加入保険料率として別に定められるため考慮されない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2428
[問題文]
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1725. seiseki2743 さん
[コメント]
「二次健康診断等給付に要した費用の額」が抜けている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2428
[問題文]
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1724. hirorin さん
[コメント]
労働福祉事業→社会復帰促進等事業です。問題訂正をお願いします。
(一般保険料に係る保険料率)
第十二条
2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
[自説の根拠]徴収法 12条2項
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2428
[問題文]
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1723. papatarou さん
[コメント]
特別支給金は機構ではなく政府、すなわち、労働基準監督署長が行う。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1189
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
労働福祉事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1722. tabasuko さん
[コメント]
独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条により、同機構が行うとされる事業は以下になります。
①療養施設(労災病院)、健康診断施設、リハビリテーション施設の設置及び運営
②未払賃金立替払事業の実施
③被災労働者に係る納骨堂の設置及び運営
[自説の根拠]独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1189
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
労働福祉事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1721. julielove さん
[コメント]
労災法
過去問:11年択一、17年択一
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1189
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
労働福祉事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日