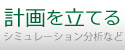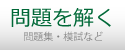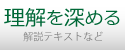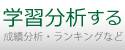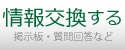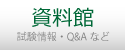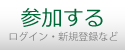社会保険労務士試験講座
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
1750. seiseki2743 さん
[コメント]
第1種特別加入保険料率
・中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率
第2種特別加入保険料率
・事業又は作業の種類に応じ、1,000分の4から1,000分の51の範囲内で、12段階の率が定められている
第3種特別加入保険料
・一律1,000分の5
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1685
[問題文]
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1749. seiseki2743 さん
[コメント]
法改正により、「労働福祉事業」に要する費用ではなく、「社会復帰促進等事業」に要する費用となる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
1685
[問題文]
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1748. syorinboy48 さん
[コメント]
労働福祉事業は× 社内復帰促進等事業が○
従い、回答は×です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
2429
[問題文]
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1747. miuuimasa さん
[コメント]
正しい
[自説の根拠]法 第32条
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2429
[問題文]
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1746. seiseki2743 さん
[コメント]
「労働福祉事業」ではなく、「社会復帰促進等事業」
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2429
[問題文]
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1745. ymamn6314 さん
[コメント]
H21の法改正により、
・短時間就労者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、40時間未満である者)
・登録型の派遣労働者
については、次のいずれにも該当する場合、被保険者となる。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して就労するものであること(6カ月以上引き続き雇用されることが見込まれること)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
674
[問題文]
次の説明は、被保険者に関する記述である。
いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派還元事業主の下で期間2か月の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して1年以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1744. mukun13 さん
[コメント]
1年以上続く見込み→6箇月以上続く見込み
に改正になりました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
674
[問題文]
次の説明は、被保険者に関する記述である。
いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派還元事業主の下で期間2か月の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して1年以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1743. daytona さん
[コメント]
次の理由により、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなった被保険者については、この期間を加算した算定対象期間となります。ただし、4年が限度です。
1.疾病または負傷(業務上外を問わない)
2.事業所の休業(事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による休業)
3.出産
4.事業主の命による外国における勤務
5.上記の理由に準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの(親族等の疾病・負傷等による看護、3歳未満の子の育児等)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
3074
[問題文]
次の説明は、基本手当の受給要件に関する記述である。
被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の1年間であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合は、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1742. seiseki2743 さん
[コメント]
設問に法改正あり
1年間→2年間(特定受給資格者の場合は1年間)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
3074
[問題文]
次の説明は、基本手当の受給要件に関する記述である。
被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の1年間であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合は、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1741. vickyvale さん
[コメント]
何で○?
算定対象期間て、また改正されて1年になったの?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3074
[問題文]
次の説明は、基本手当の受給要件に関する記述である。
被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の1年間であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合は、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日